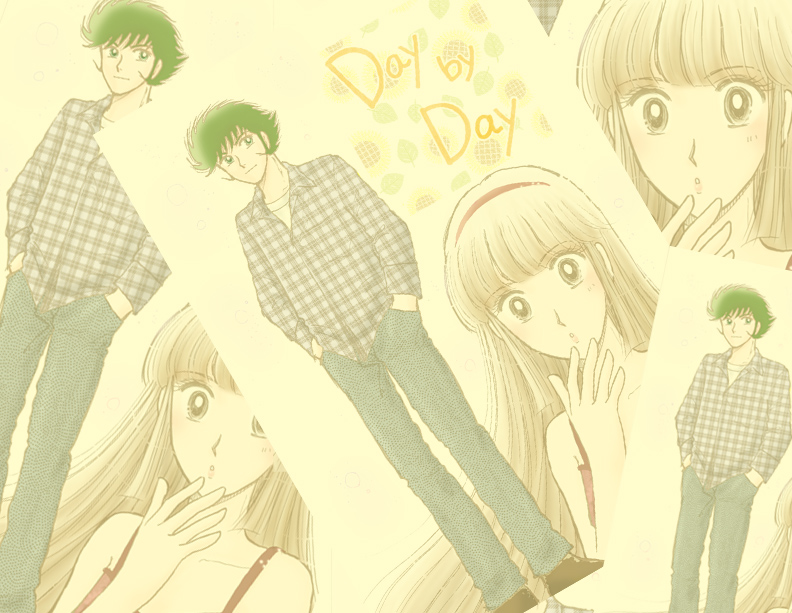
「………来ない……」
さやかは腕時計を見て溜め息をついた。
待ち合わせは二時半だったはずだ。それなのに、甲児は一向にやって来ない。
今日は甲児の発案で、映画を見た後食事をすることになっていた。甲児の選んだアクション映画はさやかも前々から見たいと思っていたものだったし、そもそもデートらしいデートは久しぶりだったので、さやかはもうずいぶん前から楽しみにしていたのだ。
それなのに。
映画の上映開始時間は三時半だというのに、すでにもう三時半を回ってしまっている。
甲児もさやかもどちらかというと時間にアバウトな性格だったので、十分や十五分の遅刻は当たり前だ。しかし、そんな甲児でもさすがに一時間の遅刻など滅多にしない。
この場合「滅多に」というのが曲者で、過去に一度甲児は一時間の遅刻をした前科持ちなのである。だから、さやかとしても一応一時間までは待ってみようと思ったわけなのだったが…。
「……ったくこの暑いのにっっ!!」
さやかは顔を上げると、真っ青な空に向かって悪態をつく。強烈な日差しが目に痛い。
こんなことなら待ち合わせ場所をもっと考えておけば良かったとこの一時間の間に何度後悔しただろう。
さやかの立っているこの場所は乗降客の多い駅の出入口だった。どうやら待ち合わせスポットになっているらしくさやかの他にも人待ち顔で立っている人が数人いるのだが、冷房もほとんど効かない場所のため暑くて仕方がない。こんなことなら、涼しい喫茶店か本屋さんで待っていることにすればよかったと思うが、約束をしたときにはまさか甲児がここまで遅れてくるとは思いもしなかったのだ。
さやかはひとつ溜め息をつく。
溜め息をつくごとに幸せが逃げていくと言ったのは一体誰だっただろう? 自分は今日だけで一体いくつの幸せを逃しているのやら。
十五分まではさやかも穏やかに待っていた。お互いこのくらいは普通に遅刻する性格なので、少しの遅刻でめくじらたてるようなことはない。あらかじめ遅刻することを計算に入れて、待ち合わせ時間を映画の上映開始より随分前にしてあるほどだ。
三十分経ってさすがに少し腹が立ってきた。甲児のマンションにも携帯にも電話を入れたが、マンションの方は留守電になったままだし、携帯には応答がない。
四十五分経つ頃にはもう帰ろうかと思いはじめた。先日のバーゲンで一目惚れして買ったワンピースには多分背中に大きな汗染みが出来ているんじゃないかと思うし、買ったばかりのミュールを履いた足は立ちっぱなしだったせいか紐が足に食い込んで痛くなってきた。
それでも、以前のこともあるしと一時間は待った。そんな自分は偉いとさやかは思う。この一時間、周りの待ち合わせの人達は次々顔ぶれが代わっていくのに、自分だけは誰も迎えに来ずずっと一人で立ったままなのだ。案外、自分を主人公に勝手な失恋ストーリーなど作り上げている暇な人間がいるんじゃないかとさえ思う。
今度甲児に会った時には、今日の詫びに、回らないお寿司を奢ってもらおうと心に決めた。
そうして一時間と少し。さやかは歩きだした。もうこれが限界だ。どこに行って何をしているのか知らないが、甲児に会って一言文句を言ってやらなければ気が済まない。
沸騰しかけた頭でそう思う反面、さすがの甲児も一時間以上の遅刻なんて珍しいから、もしかして何かあったのではないかという不安も芽生え始めていた。甲児が事故にでも遇っていたらどうしよう?
急に心配になってきたさやかは、そのまま電車に乗って甲児のマンションへ向かった。
とりあえず、甲児の顔を見なければという思いばかりが強まっていた。
甲児の現在の住まいは、光子力研究所からも近いとある賃貸マンションだった。一応恋人同士ということもあって、さやかは甲児の部屋の合鍵を貰っている。
そのあたりは緑の多い環境のいいところで、若い夫婦が多く住んでいるらしく、元気に外を駆け回る子供達の姿もよく見かける。近くにはそれなりの広さのある公園や小中学校、懐かしい感じのする商店街もあり、駅からのアクセスがバスだけしかない不便さを差し引いても、住むのに魅力を感じる街ではあった。車好きの甲児の場合、公共交通機関を使う事はあまりないので、交通の不便さは気にならないのかもしれないが。
しかし、今のさやかには問題だった。
今日は本来甲児の車に乗せてもらうはずだったから自分の車は持ってきていないし、研究所まで取りに戻るのでは時間がかかる。仕方なく電車を降りてバスを待っているのだが、そのバスがさっぱりやって来ないのだ。時間潰しを兼ねて、何度となく甲児の携帯と部屋に電話を入れたが、やはり応答はなく、さやかはイライラと足踏みしながらバス停に立っていた。こんな時、自分に煙草を吸う習慣がないことを少し残念に思う。
やっと姿が見えたバスは時刻表より随分遅れていて、そのことにもまた苛立ちながらさやかはバスに乗り込んだ。席に座ったところで、ふと見た窓には苛立って険しい顔をした自分が映っている。
「うわ、最悪……」
汗のおかげで化粧が剥げていることよりも、苛立って険しい顔をした自分が嫌だった。
さやかは気を取り直して窓の外の風景を見た。
バスは住宅街を走っていたが、夾竹桃や百日紅の花がそこここの庭で綺麗に咲いているのが見える。そんな風景を見て、心を落ちつけようとさやかは思った。
どうせ怒るのだったらイライラと神経質に怒るより、勢いよくストレートに怒りをぶつけたほうが後腐れがなくていいと長年の経験で学んでいるのだ。
窓の外の景色はどんどんと変わっていく。
もうすぐ甲児の住む街だ。怒るにせよ心配するにせよ、早く甲児の顔が見たかった。
そのままのんびりとバスに揺られ、しばらくしてさやかは甲児の住む街にたどり着いた。
しかし、勢い込んでドアを開けた甲児の部屋に、甲児本人の姿はなかった。
いろんなものが散らかりっぱなしで、何だかやけに雑然とした部屋の隅では、留守電のランプがチカチカと点滅している。放り出されたままのバッグからは、携帯が顔を覗かせている。
「これじゃあ、繋がらない筈よね」
念のために研究所にも電話をかけてみたが、甲児は今日は顔を見せていないと言う。
「一体どこへ行っちゃったのかしら……」
徐々に怒りより不安の方が大きくなってきた。もしかして本当に事故にでも遇っているのではないだろうか?
さやかは慌てて部屋を飛び出し地下駐車場へ向かった。もし出掛けていたら車がなくなっているはずだが、そこには甲児の愛車が置かれたままだ。
「甲児くん、どこ行ったの……?」
そのままあてもなくマンションの周りを歩いていたとき、やけに耳慣れた声がさやかの耳に届いた。
「………………てんだ、これっっ!?」
言葉ははっきりと聞き取れないが、これは間違いなく甲児の声だ。
それまで心配そうな顔をしていたさやかの表情が一変した。
「………甲児くんっっ!!」
目をつり上げたその顔は、なかなかに怖い。
「あたしが心配して探してたって言うのに、こんなとこで何してんのよっ!!」
声のした方を見てみると、そこには公園だった。公園といっても広大な面積を持った緑豊かで手入れの行き届いたものではなく、所謂児童公園といった程度のもので、ブランコやら滑り台、シーソーなどが置かれている。
どことなく懐かしい気のするこの公園にはさやかも何度となく来たことがあり、さやか自身好きな場所でもあった。
その公園の藤棚の下のベンチあたりに、見慣れたライオンヘアーを見つけた。
「甲児くんっっ!!」
ずかずかと公園内に入りこみ、大声で名前を呼ぶと、甲児は一瞬不思議そうな顔をして振り返り、さやかの姿を認めた瞬間、明らかに「しまった」という表情を顔に上らせた。
「今何時だと思ってるの!? まさか待ち合わせしてたの、忘れたわけじゃないでしょうね?」
「…………………………………………ごめん」
甲児は意外に素直に頭を下げる。その行動にさやかはがっくりと肩を落とした。
「もしかして………、ホントに忘れてたのね?」
「いや、今朝まではもちろん覚えてたさ。いや、今朝じゃなくてさっきまでっていうか…。でもちょっと、あの、とにかく、悪かったっっ!!」
両手を合わせて平謝り状態の甲児を見て、さやかも事情くらい聞いてやってもいいかという気になってきた。甲児の座っているベンチに置かれているドライバーやらペンチやらの工具類の意味するものも知りたかったし。
「……………で? ここで何してて約束忘れることになったわけ?」
両手を前で組んで、甲児を見下ろす。威圧感たっぷりの仕種だ。
「んー、だからさ。これ直してて…」
甲児は申し訳なさそうな顔で、手に持っていたものを差し出した。
「……これ?」
それは何やら電気仕掛けのおもちゃの部品らしきものだった。どうやら工具類はそのおもちゃを直すためのものらしい。
「何でこんなことしてんの?」
「だからさ、俺が煙草買いにコンビニ行った帰り、ここでガキが泣いててさ」
「子供?」
甲児の言葉を聞いてさやかが怪訝な顔をしたとき。
「おじさーん!!」
誰かがそう呼びながらこちらに走ってくるのが見えた。
「おじさんじゃねーって言っただろっっ!」
甲児は顔を上げるとそちらに向かって怒鳴り返す。
やって来たのは小学校五年生くらいの少年だった。
「じゃあ、『お兄さん』」
少年はしれっと言い返す。
甲児はよしよしと頷くと、少年に問いかけた。
「弟は泣き止んだか?」
「うん。今はお母さんがお菓子食べさせてるから大丈夫だけど、もし直らなかったらまた泣くと思う…」
「…………………………」
甲児は自分の手の中の部品を見て、溜め息をついた。どうやら修理作業に行き詰まりを感じているらしい。
「……もしもし?」
誰も自分に関心を向けないことに少しムッとしながらさやかが口を出した。
「どういうことかちゃんと説明してくれない?」
「だからさ、こいつの弟がおもちゃ壊して泣いてたんだよ。で、それを直してやろうと思って今まで頑張ってたわけ」
「おもちゃ……………」
デートの前に何やってんの、あんたは!!……という罵声が喉まで上がってきたが、危ういところで言葉を飲み込んだ。さすがに見ず知らずの小学生の前で醜態はさらせない。
「おもちゃの部品って…これ?」
さやかは甲児の脇に置かれているスーパー袋を覗き込んだ。色鮮やかなパーツがバラバラになって入っている。その色あいはひどく見覚えのあるものだった。
さやかはようやく納得した。自然と微笑みが顔に浮かぶ。
だから甲児はこのおもちゃを直してやろうとしたのだろう。そして直すことに夢中になって、自分との約束を忘れてしまったに違いない。
「甲児くんったら、不器用すぎるわよ?」
そう言うなりさやかは甲児の手から修理中のおもちゃの一部分を取り上げ、ベンチの隣に座り込む。お気に入りのワンピースが汚れることなどお構いなしだ。
「ドライバー取って」
さやかは、おもちゃの内部を見て、一つ一つ部品を繋いでいく。
暑い夏のこと、いくら藤棚の下で影になっているとはいえ、ここが細かい作業に向いた場所とは到底言えない。しかしさやかは、流れる汗を拭いながらも、確実な手つきで作業を進めていく。
「おおっ、さやかさん、器用!! とても料理の出来ない女だとは思えないね」
「うるさいわねっっ」
「まぁ、料理は俺が得意だし。今日はデートすっぽかしたお詫びに何か作ってやるよ」
「ホント? ならあたし、ハンバーグがいい。甲児くんのハンバーグ美味しいのよね」
「わかった。帰りにスーパー付き合えよな」
ぽんぽんと会話しながらも、さやかの手は的確に動いている。
甲児は少年と共にさやかの手元を見ているだけだ。
常日頃、どちらかというと器用なのはさやかよりむしろ甲児の方なのだが、何故かこういう細かい機械を直すことだけはさやかの得意分野だった。
「これってさ、こっちに光がつくんだよね?」
さやかは作業を進めながら、傍らでじっと自分とおもちゃと見つめている少年に聞く。
「うん。それでこっちが曲がるの」
少年は大事そうにおもちゃの部品を撫でた。
「そのロボット、元は僕のだったんだけど、今じゃ弟の宝物なんだ。弟はちょっと体が弱くって…病院にもいつもこれを持って行ってるんだ。だから……」
「わかってるって。このお姉さんに任せておけよ。あ、この人に『おばさん』なんて言ったら殴られるから気を付けろよな」
甲児が横から茶々を入れる。
「殴りゃしないわよ。蹴り飛ばすけど」
「うわー」
甲児と少年が顔を見合わせた。お互いの顔に少しばかりの恐怖を浮かんでいたのをその時二人は見た……ような気がする。
さやかは、ビニール袋から次々と部品を取り出しては、器用にそれを繋げていく。
「あのね、少年」
「なに、お姉さん」
少年はなかなか如才ない性格らしい。さっきの甲児の忠告をしっかりと守っている。
「これね、壊れた部品があるから、今は完全に直らないけど、来週部品持ってきて、ちゃんと直してあげる。そしたら、目も光るし、腕も飛ぶようになるわ。それまで我慢してって弟さんに言っておいてくれる?」一応の修理が終わったおもちゃを、さやかは少年に手渡した。甲児が長時間格闘していたにもかかわらず直せなかったことに比べると、信じられないほどの短時間で仕上げてしまったことになる。
「ありがとう」
おもちゃを受け取って、少年は心から嬉しそうに笑った。
「お兄さんもお姉さんも、ほんとにありがとう。これで弟も泣きやむと思う。来週、また来てね」
「うん。このお兄さん、あっちの茶色いマンションの305号室に住んでるから、いなかったら呼びに来てね」
さやかの言葉に少年は大きく頷くと、手を振って去っていった。直してもらったおもちゃを大事そうに抱えながら。
しばらくはその姿を見送っていたさやかが、くすりと笑って甲児を振り向いた。
「なーるほどね。だから必死になって直してあげようと思ったわけだ」
甲児は少し照れたような顔になり、あさっての方向を向く。
「壊れたままにしておくに忍びねーんだよなー。可哀相でさ」
「………………」
「それでつい、何が何でも俺が直してやるーっっ!って思っちまって、気がついたらすっげー時間が経ってたってわけ」
「気持ちはわかるけど」
さやかはちらりと上目遣いで甲児を見る。
「わかってもらって嬉しいよ。っつーことで今日のことは許してくれよな。じゃあ、帰ろうか?」
甲児はニッと笑って話の転換を図った。しかし、さやかとしてはそう簡単に話題を変えるわけにはいかなかった。
「ちょーっと待った。場合によっては許さないでもないけど、手作りハンバーグ定食だけでは物足りないのよね」
甲児の話題転換は完全に失敗したらしい。
「言っとくけど、あたし、あの暑い駅で一時間以上も一人っきりで待ってたんだからね」
「…………………………」
「映画はもう終わっちゃったし、それに今のおもちゃだって、甲児くんの代わりに直してあげたしぃ~」
さやかはちら~りと甲児を見る。
「……わかったよ。今度映画も食事も奢るから」
とうとう甲児は降参したらしい。何しろ今日は全面的に自分が悪いのだ。
「おっけー。それで手を打ってあげる」
「よろしくお願いします」
さやかが「回らないお寿司」を奢らせようとしていることなど知らない甲児はあっさりとさやかの提案を受け入れた。
もしこの約束が果たされたなら、次の給料日までしばらくの間、甲児の財政事情はかなりのピンチになることだろう。
「じゃあまあ、今日のところはハンバーグ定食作ってやるから一緒にスーパー行くか?」
「うん。じゃああたし、冷たいじゃがいものスープ作っちゃう!」
「うわ、それってマトモに食えるんだろうな?」
「失礼ねっっ!!」
いつもの会話を交わしながら、さやかは甲児と一緒に児童公園を後にした。
これから二人で甲児のマンションに帰って、ご飯を作ってテレビなんか見ながら一緒に食べよう。映画と外食は没になったけど、結局のところ、二人で一緒にいられたら、それだけで楽しいのだ。
そして来週は、少年と弟の為におもちゃ用の部品と、ついでにお菓子でも持ってここに来よう。
あのおもちゃが完全に直って、目が光ったり、腕が飛んだりするところを見たら、二人ともきっと喜ぶことだろう。
「どうしたんだ?」
急にくすくすと笑いだしたさやかに、甲児が不思議そうに問いかける。
「あの少年、甲児くんがマジンガーZの操縦者だって知ったらどんな顔するかと思って…」
少年と、病弱な弟の宝物だというそのおもちゃは、マジンガーZをかたどったロボットだった。随分使われて古びた…しかし、大事にされていたことがよくわかるロボットのおもちゃ。
何をしていて壊したのかは知らないが、それがたとえおもちゃでも、甲児はきっとZを壊れたままで放っておくことが出来なかったのだ。
そしてそれは多分自分も同じ。
アフロダイAやダイアナンA、そしてもちろんマジンガーZでも。
たとえおもちゃであったとしても、ぼろぼろになった姿は見たくない。
さやかも甲児も自分たちのロボットをこよなく愛しているのだから。
「さやか、それ、あのガキ共に言うなよ?」
「なんで?」
「なんででもっっ!!」
甲児は急に早足になって歩きだした。その背中が照れているのがわかる。
さやかはもう一度くすりと笑うと、甲児の後を追って駆けだしていった。
おしまい
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで