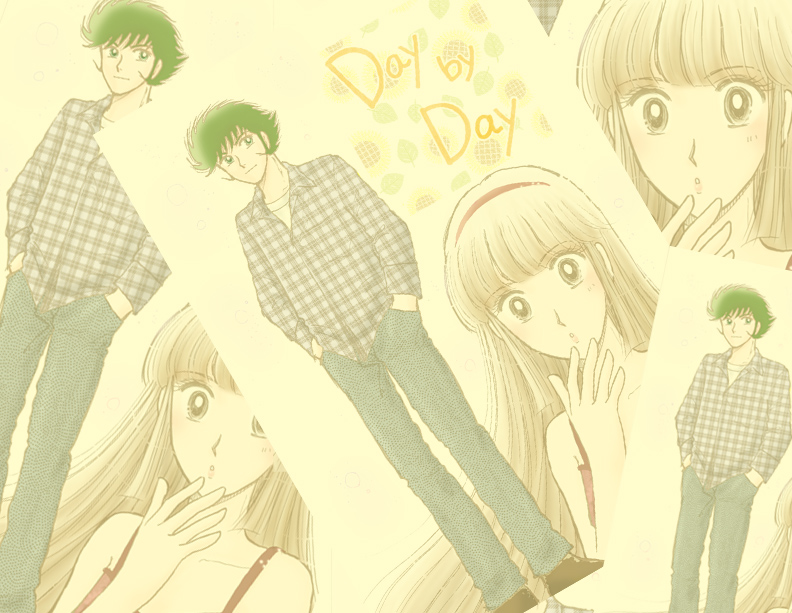
「さやかが倒れた!?」
それは、研究所に入った一本の電話が始まりだった。
病院からの突然の電話。
電話の向こうの誰かは焦った声で話している。
さやかが倒れたこと、今病院にいること、病院の場所と……後はよく聞き取れない。いや、電話の向こうの声は延々と続いていたのだが、甲児の耳には入ってこなかったのだ。
全身の血が一気に引いていく。足元が急にふわふわと頼り無いものになってしまった気がする。
昨日会ったとき、さやかは元気にしていたはずだ。ちょうど休みが重なったから、一緒に野球を見に行って、夜のドライブを楽しみながら帰ってきた。
研究所の前で降ろしたあと、去っていく甲児の車に向かって手を振ってくれていたさやかの姿が目に浮かぶ。
現在甲児は研究所近くのマンションを借りて生活しているから、以前のようにさやかと一つ屋根の下に住んでいるわけではない。だから、昨夜別れたあとのさやかに何があったかは知らないが、それでも、昨日のさやかはいつもと変わらず全く普通で、体調が悪いとか、気分がすぐれないとか、そんなことは一言も言っていなかった。むしろ、この酷暑で夏バテする人も多い中、元気すぎるほどだったのだ。
ここのところ二人の仲はとても順調だった。二人がそれぞれの留学先から帰ってきてすぐは、仕事が忙しすぎたり、二人の事情を知らない新しい若手所員達が甲児とさやかそれぞれを狙ってみたりしたおかげで、ちょっとした波風が立ちもしたのだが、恒例の大喧嘩をした後は二人にちょっかいをかけようとする強者は誰もいなくなり、所内的にもなるべく二人の休みを合わせてやろう(そうでないとまた喧嘩騒ぎが起こるかもしれないという懸念があったので)という心遣いをしてくれるようになったこともあって、至って平和に過ごしている。
それなのに…。
「甲児くん?」
電話に出た甲児の顔色が変わったのに気づいたみさとが、怪訝な顔で名前を呼んだ。
「甲児くん、顔色悪いわよ? どうしたの? どこからの電話?」
けれど、甲児はみさとの呼びかけに反応することなく、電話を置くと休憩室から走り出した。
「甲児くんっっ!!」
後ろからみさとの呼んでいる声がするが、今の甲児の耳には入らなかった。
今の甲児の頭にあるのは、さやかのいる病院に一刻も早く駆けつけなければ…というそれだけだった。
もしも今、自分の傍からさやかという存在が失われたら…そうしたら、自分は一体どうすればいいのだろう?
昔は毎日死と隣り合わせの生活をしていたはずなのに、あの頃には感じなかった恐怖が甲児の背中を伝っていく。さやかを失うことが怖い。さやかがいなくなるなど、今の自分には考えられない。
研究所のドアを開けて外に出る。
とたんに、もわっとした熱気が甲児の体を包んだ。
今日も日差しがきつく、じっとしていると汗が吹き出してくるほどだ。それなのに甲児の体は芯から冷えきっていて、熱気を感じることも汗を出すことすら忘れているようだった。
一目散に駐車場に走り、愛車を出す。
頭の中で、さっきの電話で誰かが説明していた病院の場所を思い浮かべる。
そのあとは、もう、自分がどうやって車を運転していたのかも甲児には思い出すことができなかった。
病院というのはどうしてこうも暗い感じがするのだろう?
甲児はそう思いながら、さやかが収容されたという病院に足を踏み入れた。
清潔だが無機的な印象の病院内は、外の気温にくらべると寒いくらいだ。待合室には年配の男女が大勢いて、ひそやかな会話が交わされている。
甲児は受付の窓口に近づいていき、さやかのことを聞こうとした。
そのとき。
「あれ、甲児くん?」
背後から限りなく耳慣れた声が聞こえてきて、ぎょっとした甲児は慌てて振り向いた。
そこには……。
「……さ…さやか……?」
そこに立っていたのは倒れたはずのさやか本人だった。
「おまえっ、なんで……え……?」
頭が混乱する。さやかは急に倒れてここに運ばれてきたのではなかったのか? なのに今の彼女は少し日焼けまでして至って健康そうな様子だ。
「ありがとう、迎えに来てくれて。ここから研究所までって結構距離あるから、自力で帰るの大変だって思ってたのよね」
「…………………………」
いつもと全く変わりない様子で話すさやかを、現状把握ができない甲児は、半ば呆然としたまま見つめることしかできなかった。
「ほんとにもう、参っちゃうわね、この暑さったら」
「…………………………」
「夏は暑いもんだってわかってるけど、今年はちょっと異常だわよね?」
「………………………」
「ヨーロッパの方もひどい暑さなんですって?」
「…………ちょーっと……、待て」
いつもの調子で話しているさやかを、気を取り直した甲児が止めた。
「……………ちょっとお聞きしたいんですけどー?」
「はい?」
さやかはきょとんとした顔で甲児を見返している。
「さやか……、おまえ、倒れたんじゃ……ねーの?」
「あたし? うん、倒れたわよ?」
「なら、何でそんなに元気そうにしてんだよっ!」
「だから、日射病だったんだって」
「日射病…」
甲児は呆然とさやかの口にした病名を繰り返す。
「今日はお休みだったし、テニスコートの予約取れたからテニスしに行ったんだけど、この暑さでしょう? それにここんとこ仕事が立て込んでたし、昨日は遅くまで騒いでたし…。どうも疲れも溜まってたらしくて、で、テニスしてるうちにふらふらってなっちゃって、病院に担ぎ込まれたってわけ。そしたら日射病だったんですって。しばらく寝てたら治っちゃった。テニスのコーチがそう研究所に電話してくれたと思うんだけど?」
「………………………………………」
確かに電話の声は、病院の名前と場所告げたあと、なにやらごちゃごちゃ言っていたような気がする。しかし、「さやかが倒れた」という部分だけで思考の止まってしまった甲児にはそれ以上の説明は聞こえなかったのだ。
「……そ……そう………」
廊下に置かれていた長椅子にがっくりとへたりこむ。
「どうしたの?」 「…………………………」
さやかが不思議そうに甲児の顔を覗き込む。
そんな彼女にどんよりとした笑顔を返して、甲児は思った。
電話を受けてからついさっきまでの自分の苦悩は一体何だったのだろう?
日射病なら日射病とさっさと言え!!
……そりゃあ確かに、日射病もひどくなると命に係わる病気だから決して馬鹿には出来ないが、それにしても「倒れた」という表現からはもっと別の大病を連想するのが普通だろう。テニスのコーチとやらも、きちんと順序を考えて話せっっ!
甲児は心の中で研究所に電話してきたテニスのコーチとやらに蹴りを入れた。本人がもう帰ってしまったのが残念だ。
「………おまえさ……」
甲児は顔を上げて、さやかをじっと見た。
「なに?」
「今度からは、テニスするときは帽子被ってやれよな」
甲児は曖昧な笑いを唇の辺りにはりつけている。その表情は脱力感でいっぱいだ。しかしさやかは、甲児の内心など知るよしもなくボケた台詞を口にした。
「えー? あたし、そんなに焼けてる? 日焼け止めは塗ってたんだけどなぁ…」
「そーゆーことを言ってるんじゃねぇ……」
ちょっとキレかけた甲児がさやかをぎろりと睨んだ。
睨まれたさやかの方は、相変わらず訳がわからないらしく、きょとんとした顔をしている。
さやかの顔は疑問符でいっぱいだったが、甲児はさやかに自分が誤解したということを説明するつもりはなかった。そんなことをしたら、自分が、「さやかが倒れた」という一言で動揺しまくったことを白状しなければならなくなる。そんな恥ずかしいことは絶対に御免だった。
「ま、いいから帰ろうぜ。帰りにどっかで冷たいモン飲んで行こう」
「いいわねー」
そのまま二人はひんやりした病院を後にして、酷暑の屋外に出た。
炎天下に停めてあった車の中は、乗ったとたんに汗が吹き出すほど暑い。さっきはこの暑ささえ感じなかったのだと思うと、何だか不思議だ。
甲児は、みさとに何と説明して誤魔化せばいいのか、帰りの喫茶店でゆっくり考えようと思った。本当のことは言いたくないが、勘のいいみさとはなかなか手ごわいのだ。
それに、考えなければならない言い訳は、みさとに対するものだけではない。
電話がかかってきたのが午後の休憩時間だったため、甲児はそのあとの仕事を放り出してきてしまったのだ。
『さやかのおかげでとんだ災難だよ…』
そう嘆きつつも、さやかが今この瞬間、車の助手席に座っていることに安堵している自分を甲児は自覚していた。
さやかは、ここにいる。
それはとても幸せな事実だった。
ともあれ。
夏の日射病と熱中症にはご用心下さい……。
おしまい
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで